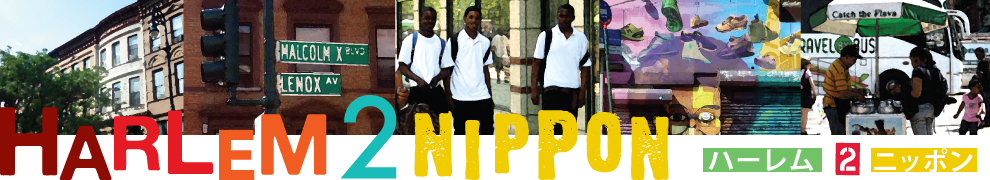バリー・ジェンキンス監督の新作、ジェームズ・ボールドウィン原作の、『If Beale Street Could Talk』が12月14日(金)封切りになりました。マンハッタンでは、リンカーン・センターの「AMC Loews Lincoln Square 13」と、ダウンタウンの「アンジェリカ・フィルム・センター」の二か所のみですが、好調なスタートのようです。初日の金曜日には、ジェンキンス監督と、女優のレジーナ・キングが劇場に駆けつけ、挨拶、質疑応答を行うことになっています。
ビール・ストリートの恋人たち Fonny and Tish
ハーレムの公園を歩く、主人公のフォニーことAlonzo Hunt、 22歳と、恋人のティッシュ、19歳を頭上から追っていくシーンから始まります。1970年代が舞台なので、ファッションや髪形も当時を復元しています。細やかな映像で知られるジェンキンス監督、昔の良きハーレムを再現してくれます。
希望に満ちた若いカップルの爽やかなオープニング・シーン…….、そして、恋人のフォニーが、今は刑務所のガラス越しにいる、という現実…….。ティッシュは、フォニーに「あなた、父親になるのよ。」と自分が妊娠していることを告げます。ティッシュは母にも話し、フォニーの家族を呼び寄せ、新しい命が育まれていることを伝えます。この小さな命がこの物語の始まりです。
獄中にいるフォニーと、過去のふたりのエピソードが交錯します。フラッシュ・バックが多いので、ちょっと分かりにくいかも知れません。
フォニーの昔の友達、ダニエルにばったり会います。ぽつり、ぽつり、ダニエルはこれまで何があったか話し出します。車の運転もできないのに、車の窃盗犯としての濡れ衣をかけられ、なすすべもなく、2年間服役して出てきたばかり…….。刑務所の中では想像を絶するような忌まわしい出来事が日常茶飯事に起きている……..。楽天家でひょうきんだったダニエルに、昔の面影はありませんでした……。「白人は悪魔だ…..」とダニエルは言います。「あいつら、やろうと思えば俺たちに何だってできるんだ。they can do with you whatever they want……whatever they want」、黒人の男たちはそれが何を意味するか、痛いほどわかっているのです。ここはビール・ストリート(黒人社会)だから…….。
ふたりの家族は、力を合わせてフォニーを釈放してもらおうと奔走します。ティッシュの姉のつてで、ジューイッシュの若手の弁護士を紹介してもらいます。黒人の弁護をしてくれる弁護士は多くはありません。まだ経験の浅いヘイワードですが、他に弁護してくれるベターな候補者がいないのです。貧困なハーレムの住人にとって、ヘイワードの弁護士費用を捻出することは容易ではありません。ティッシュの父親は港で荷役として働いています。めいっぱい残業し、少しでも稼ぎを増やそうとがんばります。ガーメント・ディストリクトの衣料問屋で働くフォニーの父親、フランクも同様、できるだけ長時間働いて収入を増やそうと努力します。まともに働いてもロクな給料をもらえない、ほとんど日雇いのような黒人の男たちには明るい未来はないかのよう。ふたりは、よこしまなことを考えます。職場の商品を横流しし、小遣い稼ぎをします。
レイシスト警官、ベルの罠
フォニーは、自分が逮捕されたのは、以前接触のあった白人警官、ベルの仕業だと信じ込みます。ビレッジのデリでティッシュがチンピラにからまれていたのをみつけ、そいつを殴って痛めつけた時、あの忌まわしいベルがやってきたのでした。まるで、フォニーを犯罪者のように扱い、連行しようとしたベル。たまたま、デリのオーナーのイタリア人のおばさんがその場を収めてくれて難を逃れたのですが、ベルの、「今度会ったら…….(覚えていろよ)」という葉が脳裏に焼き付いていました。
プエルトカンのビクトリアがレイプされたと通報を受けたベル。犯人の唯一の手がかりは「黒人」というだけ。警官ベルは、フォニーのダウンタウンの棲み家のドアを叩き、彼を連行したのでした。その時、フォニーの他にティッシュとダニエルがいて、十分なアリバイがあったにもかかわらず、です。事件が起きたのはローアー・イーストサイドのオーチャード・ストリート、そして、フォニーの家はウエスト・ビレッジのバンク・ストリート、どう考えても犯行のあと走って逃げてこれる距離ではありません。「あの時の逆恨みに違いない、……。」フォニーは背筋が震えるのを感じます。
フォニーは、容疑者として被害者のビクトリアの前に突き出されます。他にもプエルトカンや浅黒い男たちが並ばされました。「この男です。」と女はフォニーを指さしました。唯一の黒人がフォニーだったからです。女の一言でフォニーは刑務所にぶち込まれました。「あいつら(白人)は、やろうと思えば俺たちに何だってできるんだ。」吐き捨てるように言ったダニエルの言葉が蘇ってきます。
「あの女は嘘をついている。」、ティッシュの家族は、プエルトリカンの女、ビクトリアを探し出し、証言を撤回させようと作戦を立てます。そのさなか、ビクトリアは姿を消してしまいます。
ジェンキンス監督は、原作に忠実に描いてゆきます。ジャズや当時のR&B音楽を散りばめ、裸電球のまぶしい光に焦点を当てるなど、きっと作者のジェームス・ボールドウィンもこんなビジュアルを想定していたのかもしれない、と思わせるような見事なディレクションです。
ありえない結末…..!
ぶじに男の子を出産したティッシュ、生まれたばかりの赤ちゃんと入浴して母親になった喜びをかみしめるピースフルなシーン。エンディングは、息子を連れたティッシュが刑務所に面会に訪れ、家族3人でスナックを食べながら笑っている…….、え? まるでハッピー・エンドのような結末…….。あまり絶望的なエンディングにしたくない、という気持ちがあったのかも知れませんが、これはジェンキンス監督の創作であって、ボールドウィンが意図した結末ではありません。
原作では、ようやく保釈金のメドがつき、フォニーがティッシュのもとに帰ってこられる日も間近、という矢先にフォニーの父親が自殺してしまうのです。フォニーの保釈金をかき集めるために、フランクは危険を承知でたびたび職場で盗みをはたらいていて、それが発覚し、その場でクビになってしまいます。泥酔して家に帰ってきて、またすぐに外出したまま行方不明になっていたフランク。2日後、ハドソン川上流の森林で死体となって発見されます。フランクの死は、黒人たちのおかれた劣悪な環境を象徴しているのだと思います。人間らしく生きてゆくこともままならない黒人の男たち。悲惨な現実ではあるけれど、どこにも逃げ道がない……、それがボールドウィンの描く世界なのではないかと思います。
結末には異議あり、ですが、ボールドウィンの作品を映画化してくれたバリー・ジェンキンスには感謝。もっとこういう映画が多く制作されることを願っています。
伊藤 弥住子